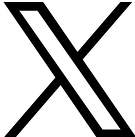ピラティスは肩こりに効く?マシンピラティスが効果的な理由も解説
「ピラティスは肩こりにいいって本当?」
「家でも取り入れられるのかな?」
ピラティスは姿勢を本来の位置に近づけることを目指すエクササイズで、その過程で肩こりの軽減にもアプローチできるといわれています。
また、ゆったりとした動きが中心のため、体力に自信のない方や初めての方でも取り入れやすいのが特徴です。
この記事では、ピラティスで肩まわりが楽になりやすい理由や、おすすめの頻度と期間、自宅でできる簡単なメニューまで順番に説明していきます。
ピラティスを続けながら、肩こりの少ない生活を目指していきましょう。
ピラティスで肩こり緩和が期待できるのはなぜ?4つの理由をやさしく解説

ピラティスが肩こりケアのサポートに良いといわれているのは、体の使い方を根本から整えるアプローチが期待できるためです。
肩や首の筋肉を直接ほぐすだけでなく、姿勢・呼吸・筋肉バランスに働きかけることで、こりの原因そのものにアプローチしやすくなります。
日常生活では、スマホやパソコン作業で前かがみの姿勢になりやすく、想像以上に肩や首に負担がかかっていますよね。
ピラティスでは、体幹を中心に正しい姿勢を保つ力を育てていくため、肩まわりがリラックスしやすい状態を目指せます。
さらに、胸式呼吸を用いることで呼吸が深まりやすくなり、無意識に力が入りがちな肩や首も、リラックスした状態に戻りやすくなります。
肩甲骨まわりの動きがよくなることで血流が促され、代謝アップも期待でき、肩こりが起こりにくいコンディションづくりへと導きます。
そもそも肩こりの原因とは?ひどくなりやすい人の特徴
肩こりの主な原因は、同じ姿勢を長時間続けることで起こる筋肉の緊張だといわれています。
特にデスクワークやスマートフォンの操作で前かがみになると、首から肩にかけての筋肉が常に引っ張られた状態になり、血流が悪くなって酸素や栄養が届きにくくなることで、痛みや重だるさにつながります。
加えて、運動不足やストレスも肩こりを悪化させやすい要因です。
体を動かす機会が少ないと筋肉が硬くなりやすく、さらに血行が滞りがちになります。
また精神的な緊張が続くと、無意識に肩をすくめて力が入りやすくなる点も見逃せません。
特に、猫背気味の人や冷え性の人は、肩こりが慢性化しやすい傾向にあります。
筋肉のこりは姿勢や生活習慣の積み重ねで生じるものなので、日々の体の使い方を見直すことが大切です。
ピラティスはその土台を整えるサポートとして取り入れやすいエクササイズといえるでしょう。
姿勢を整えて首・肩の負担軽減を目指す
肩こりの多くは姿勢のくずれから始まります。
背中が丸まると頭の位置が前に出て、重い頭を支えるために首や肩の筋肉が常に緊張しやすい状態になります。
ピラティスでは、背骨の自然なカーブを意識しながら動くため、正しい姿勢を保つ感覚が身につきやすくなります。
たとえば「ロールアップ」のような動きでは、腹筋と背筋をバランスよく使い、背骨を一つずつ丁寧に動かしていきます。
「ロールアップ」はマットピラティスの代表的なエクササイズで、腹筋のコントロールと背骨の柔軟性にアプローチする基本の動きです。
仰向けから背骨を一つひとつ丸めるように起き上がり、お腹の力で上体を起こしていきます。
この感覚が体に定着してくると、日常生活でも無理なく姿勢をキープしやすくなっていくでしょう。
姿勢が整うことで肩や首の筋肉が本来の働きをしやすくなり、余計な力みが減るため筋肉の緊張がやわらぎ、肩こりが軽く感じることができるかもしれません。
肩甲骨の動きが滑らかになる
肩こりを和らげるには、肩甲骨まわりの動きをスムーズにすることが欠かせません。
肩甲骨は腕・背中・首の筋肉とつながっていて、動きが硬くなると血流が滞りやすく、こりを感じやすくなります。
ピラティスでは「スキャプラセッティング」などのエクササイズで、肩甲骨の位置を意識しながら動かしていきます。
「スキャプラセッティング」は、肩甲骨を本来の位置に近づけて安定させることを目的とした、ピラティスの基本ともいえる動作です。
この練習を続けることで、普段あまり使われていない小さな筋肉まで目覚めやすくなり、肩甲骨が滑らかに動く準備が整っていきます。
肩甲骨が自由に動くようになると、肩や腕の可動域も広がり、動かすたびに筋肉が自然にゆるむ感覚が生まれやすくなります。
あわせて血行が促進されることで、肩の冷えやむくみの軽減にもつながり、硬さが取れてくると深い呼吸がしやすくなり、リラックスした状態を保ちやすくなるでしょう。
胸式呼吸で肩の力が抜ける
ピラティスで行う胸式呼吸は、肋骨を左右と後ろに広げるように息を吸い、吐くときにお腹を軽く引き締める呼吸法です。
この呼吸を繰り返すことで、肩や首に余分な力を入れずに体を支える感覚が身につきやすくなります。
浅い呼吸になりやすい人は、首や肩に力を入れて呼吸している場合も多いため、意識して胸式呼吸に切り替えていくことがポイントです。
胸式呼吸を続けると、胸まわりや肋骨まわりの筋肉がしなやかになり、自然と肩の力を抜きやすくなります。
それによって血流やリンパの流れを促し、冷えやこりの予防にもつながると考えられています。
日常の中でも、この呼吸法を数回取り入れるだけで肩まわりの緊張がほぐれやすくなるでしょう。
仕事の合間や家事のすき間時間に試してみると、体がすっと軽く感じられるかもしれません。
体幹を使えるようになり肩に頼らなくなる
肩こりに悩む人の多くは、動くときに肩や腕の筋肉ばかりに頼ってしまいがちです。
ピラティスでは、体の中心である体幹を使って動くことを丁寧に学んでいきます。
体幹がしっかり働くようになると、これまで肩や首に集中していた負担が分散され、こりにくい体へと変化していくことが期待できるでしょう。
たとえば「ボトムリフト」では、お腹やお尻の筋肉を意識して体を支えるため、自然と上半身だけに頼らない動きが身につきます。
体幹が安定すると、肩は補助的に使われる役割が増え、無駄な力みを減らしながら姿勢を保ちやすくなります。
その結果として筋肉の疲労感が少なくなり、肩こりが起こりにくい体づくりにつながっていくでしょう。
ピラティスで肩こり改善を目指すなら?おすすめの頻度・期間・スタジオ活用術

肩こりを少しでも早く軽くしたいときは、「どのくらいの頻度で通うか」「どれくらいの期間続けるか」をざっくり決めておくとペースがつかみやすくなります。
あわせて、スタジオの選び方や通い方のイメージを持っておくと迷いにくくなるでしょう。
ここでは、通う回数の目安と変化を感じ始める時期、グループとパーソナルの使い分け、オンラインの取り入れ方まで、無理なく続けるためのポイントを紹介します。
効果を実感しやすいのは週2〜3回
最初は週1回からでも構いませんが、体に新しい動きがなじむまでは、週2回程度のリズムにすると姿勢や呼吸の感覚が途切れにくく、肩の軽さも感じやすくなります。
デスクワークが多い人やこりが強い人は、最初の4週間だけ週3回に増やすと、硬さが戻りにくく、可動域の変化にも気づきやすいでしょう。
ただし、頻度を上げれば上げるほど良いというわけではなく、睡眠や栄養と合わせて回復時間を確保することが、疲労をためずに続けるためには大切です。
忙しい週は「スタジオ1回+自宅での短い復習エクササイズ」といった形にすると、無理なく週2回分くらいの刺激をキープしやすくなります。
ピラティスで体の変化を感じるのは1カ月〜が目安
個人差はありますが、姿勢の意識や肩の軽さといった体感は、通い始めて2週目以降から出始めることが多いです。
見た目の変化や、楽な状態が続く感覚は、およそ1カ月を過ぎた頃から感じやすくなるでしょう。
週2回程度のペースを維持できると、肩甲骨まわりの筋肉が働きやすくなり、呼吸の深さも安定してきます。
その結果、日中の「こり戻り」が少なくなり、仕事や家事を終えたときの張り感が和らいだと感じる人もいます。
さらに3カ月ほど続けると、土台となる体力や体幹のコントロールが自然に身についてきて、通う回数を少し減らしても調子を保ちやすくなるでしょう。
焦らずカレンダーなどに簡単な記録をつけ、睡眠の質やエクササイズ後の疲れ方と合わせて振り返ると、自分なりのペースがつかみやすくなります。
グループレッスン・パーソナルレッスンを使い分ける
コストを抑えつつ習慣化したいならグループレッスン、癖の修正や痛みの背景までしっかり見てほしいならパーソナルレッスン、といった選び方がおすすめです。
たとえば、最初の数回はパーソナルで姿勢評価と基礎づくりに集中し、その後はグループで反復練習、1カ月ごとにパーソナルで微調整を受ける、といった流れにすると学びと定着の両方を進めやすくなります。
グループレッスンは、他の人の動きから気づきを得られたり、エクササイズ量を確保しやすいところがメリットです。
ただし細かい手直しは受けにくい場合もあるので、気になる点はレッスン中や終了後に質問するといいでしょう。
パーソナルレッスンでは実際に体に触れながら調整してもらえたり、マシンの細かなセッティングをしてもらえたり、安全かつ肩に負担の少ないフォームを身につけやすくなります。
肩こりの根本原因まで見直したい人には心強い選択肢になるでしょう。
オンラインレッスンの併用でより効果を実感しやすく
通う時間が限られている人は、スタジオレッスンとオンラインレッスンを組み合わせると、エクササイズの回数を保ちやすくなります。
ライブ配信なら講師が画面越しにフォームをチェックしてくれるため、自宅にいながらも基本の動きを確認しやすいのがメリットです。
録画配信のレッスンであれば、移動の合間や就寝前などの短時間で復習ができ、スタジオで習った感覚を日常に持ち帰りやすくなります。
事前に通信環境とカメラ位置を整え、マットとできれば全身が映る鏡を用意しておくと安心です。
鏡で自分の姿を確認しながら動くことで、肩甲骨の動きもつかみやすくなります。
スタジオレッスンでは少し強度を上げ、オンラインレッスンでは基礎と呼吸を丁寧に見直す、といった役割分担にすると、無理なくレベルアップを目指しやすいでしょう。
肩こりにはマシンピラティスとマットピラティスどちらがおすすめ?

マシンピラティスとマットピラティスで迷うときは、今の肩こりの強さや巻き肩の程度、通いやすさを基準に考えてみるのがおすすめです。
マシンは姿勢を支えながら狙った筋肉にアプローチしやすく、マットは少ない道具で習慣化しやすい、という違いがあります。
ここでは、それぞれの特徴と肩こりへのアプローチの仕方をお伝えするので、自分に合いそうなスタイルをイメージしながら読んでみてください。
マシンピラティスは肩こりや巻き肩が強くても始めやすい
マシンピラティスは、スプリングの補助で体を理想的な位置に導いてくれるため、肩をすくめやすい人や巻き肩が強い人でも、力みすぎずに動きを学びやすいエクササイズです。
負担が全身に分散されるので、首や肩の緊張が強い日でもフォームが大きく崩れにくく、呼吸に意識を向ける余裕が生まれやすいでしょう。
リフォーマーやキャデラックでは、ストラップの向きやバネの強さを調整することで、肩甲骨の滑らかな動きと体幹の安定を同時に引き出しやすくなります。
インストラクターの姿勢評価に基づいてセッティングしてもらえるので、癖の修正が進みやすく、比較的短い期間でも肩の軽さを実感しやすいでしょう。
特に、マシンピラティス×パーソナルレッスンの組み合わせは、肩こりケアを期待される方に向いています。
マットピラティスは自重で無理なく始めやすい
マットピラティスは自分の体重を使ってコントロール力を磨いていくスタイルで、道具が少なくても始めやすく、週のすき間時間にこまめに続けやすいのが魅力です。
床から伝わる感覚を頼りに背骨を丁寧に動かすことで、肩甲骨まわりの細かな筋肉までしっかり効かせることが期待できます。
体に負担の少ない範囲で練習でき、呼吸や姿勢への意識も日常生活に取り入れやすいため、こり戻りを防ぐためのセルフメンテナンスとしても相性が良いエクササイズです。
スキャプラセッティングやペルビックカールなどの基礎種目を積み重ねると、デスクワーク中の姿勢が安定しやすくなり、肩まわりの張り軽減を感じられる人もいるでしょう。
初心者さんにはマシンピラティスがおすすめ
ピラティスが初めての方や肩こりが強い方は、まずマシンで安全な動き方と筋肉バランスを体感するところから始めるのがおすすめです。
マシンピラティスは負荷やサポートを細かく調整できるため、自分に合った範囲で少しずつ動きに慣れていきやすく、痛みを避けながら目標に近づいていくことができます。
インストラクターのサポートのもとで体幹を使う感覚が分かってくると、肩の力がふっと抜ける感覚がつかみやすくなり、呼吸も自然と深まりやすくなります。
慣れてきたら、通いやすさや費用に合わせてマットピラティスも取り入れたり、自宅でオンラインレッスンを活用したりするのも良い方法です。
スタジオではフォーム確認とステップアップ、自宅では短時間の復習やリセットタイム、というように役割を分けると、忙しい日でも調子をキープしやすくなります。
ピラティスで肩こりを悪化させないための注意点
正しい方法で行えば、ピラティスは肩こり緩和に期待できるエクササイズですが、やり方を間違えると、かえって肩や首に負担をかけてしまうこともあります。
ここでは、肩をすくめたり腰を反らせすぎたりしないコツ、呼吸を止めないための意識の持ち方、痛みやしびれを感じたときの対応について解説します。
安心して続けるために、ぜひ一度チェックしてみてください。
肩をすくめる・腰を反る動きは控える
ピラティス中に肩をすくめてしまうと、首や肩の筋肉に余分な緊張が加わり、こりを悪化させる原因になりかねません。
特に腕を上げる動作では、肩甲骨をやや下げるようなイメージを持ち、首の付け根に力が入りすぎないよう意識することが大切です。
また、姿勢をよくしようとして腰を反らせすぎるのも注意が必要です。背中の緊張が強まり、肩の位置が前に出てしまうと、反り腰や巻き肩につながる場合もあります。
動作中はお腹を軽く引き込み、背骨を長く保つイメージを持つと、自然と体幹が働きやすくなり、無理なく姿勢を保てるでしょう。
レッスン中は鏡でフォームを確認したり、インストラクターにこまめに見てもらったりすると安心です。
呼吸を止めると首や肩に力が入りやすい
ピラティスで肩こりケアを目指すときは、「呼吸を止めずに動くこと」がとても重要になります。
息を止めてしまうと胸や首まわりに余計な力が入り、筋肉が硬くなりやすくなってしまいます。
動きに集中しすぎると呼吸が浅くなりがちなので、「吸って・吐いて」のリズムを口に出さず心の中でカウントするのも一つの工夫です。
胸式呼吸を使うことで肋骨がよく動き、肩まわりの緊張が自然とほどけていきやすくなります。呼吸に合わせて体を動かすことで、全身のバランスも整い、血流アップも期待できます。
もし動作中に息苦しさを感じたら、一度動きを止めて楽な姿勢に戻り、ゆっくり数回深呼吸してから再開すると安心です。
しびれや痛みがある肩こりは、まず医療機関を受診
肩こりの中には、単なる筋肉のこりではなく、神経や関節のトラブルが隠れているケースもあります。
しびれや鋭い痛みが出る場合は、自己判断でストレッチやピラティスを続けるのではなく、整形外科などの医療機関に相談しましょう。
頚椎のゆがみや神経圧迫がある状態で無理な動きを続けると、症状が悪化するおそれもあります。
医師の診断を受け、エクササイズの可否や注意点を確認したうえで、軽めの動きから始めるとより安心です。
ピラティスはリハビリの一環として取り入れられることもあり、安全性の高いエクササイズといわれていますが、痛みを我慢して行うと十分な効果が得られにくくなります。
その日の体調に合わせて強度を調整し、「心地よく動ける範囲」を守ることが、長く続けるための第一歩です。
自宅ピラティスで肩こりケア!簡単にできるエクササイズ5選

スタジオに行けない日でも、自宅でできるピラティスを取り入れることで、肩まわりのこりをやわらげることが期待できます。
ここでは、道具を使わずに行える基本の5つのエクササイズを紹介します。
どれも短時間でできるので、デスクワークの合間や寝る前にも取り入れやすい内容です。
また、始める前に背筋を軽く伸ばし、胸式呼吸で呼吸を整えておきましょう。
肋骨に空気を入れるイメージで息を吸い、吐くときにお腹を少し引き込むと、肩の力が抜けやすくなりますよ。
スキャプラセッティング
肩甲骨まわりを目覚めさせる、基本のエクササイズです。
- 背筋を伸ばして立つ、または四つんばいの姿勢になる
- 息を吸いながら肩甲骨を背中の中央に軽く寄せる
- 息を吐きながら、肩をすくめないようにそっと元の位置に戻す
首を長く保ち、耳と肩の距離を遠ざける意識を持つことがポイントです。
この動きを繰り返すことで、肩甲骨の動きがスムーズになり、背中の深い部分の筋肉がじんわり目覚めていきます。
慣れてきたら、腕を前に伸ばした状態で行うと、さらに意識しやすくなります。
毎日1分ほど続けるだけでも、デスクワークで固まりやすい肩の周辺が温まり、血流の変化を感じられるでしょう。
スワン・プレップ
うつ伏せから上半身を持ち上げ、背中の筋肉を使いながら姿勢にアプローチするエクササイズです。
- うつ伏せになり、胸の横あたりに手を置く
- 息を吸いながら、腰を反らせすぎない範囲で胸を軽く持ち上げる
- 吐きながらゆっくりと元の位置に戻す
腰が反りやすく痛みを感じやすい方は、吸う息ではなく吐く息で胸を持ち上げると、コアの筋肉が働きやすく腰周りを守りながら動くことができます。
同時に、肩甲骨をやや下げるつもりで動くと、肩まわりの力が抜けて首が伸ばしやすくなります。
スワン・プレップを継続していくと、猫背傾向の改善や胸の開きやすさにつながり、巻き肩対策としても役立つでしょう。
スレッド・ザ・ニードル
四つんばいから片腕を床に通すようにして、背骨と肩甲骨をねじるエクササイズです。
- 四つんばいの姿勢になる
- 息を吐きながら、片腕を反対側の腕の下にくぐらせるようにして体をねじる
- 吸いながら腕を戻し、元の姿勢に戻る
動作のたびに背中や肩甲骨まわりの筋肉が伸び、血流促進が期待できます。
ねじるときは、腰や肩に力を入れすぎず、胸からひねるイメージを持つと安全です。
動作の終わりに数秒キープすると、ストレッチ感が深まりやすくなります。
スレッド・ザ・ニードルは、左右差のリセットにも役立つエクササイズなので、姿勢のバランスを整えたい人にもおすすめです。
ウォール・エンジェル
壁を背もたれ代わりに使い、腕を天使の羽のように動かすエクササイズです。
- 壁に背中をつけて立ち、かかと・背中・後頭部をできる範囲で壁に近づける
- 息を吸いながら、肘を軽く曲げた腕をゆっくりと上にスライドさせる
- 吐きながら腕を下ろしていく
肩がすくまないように注意し、肩甲骨を下げる意識を持ちながら動かすのがポイントです。
壁に沿って腕を動かすことで、自然と正しい姿勢を確認しやすくなり、肩まわりの筋肉も心地よく伸びていきます。
家事やデスクワークの合間に1分ほど取り入れるだけでも、血流が促進されて肩の軽さを感じる人の多いエクササイズです。
ペルビックカール
仰向けで骨盤を持ち上げていき、体幹にアプローチしながら背骨を丁寧に動かすエクササイズです。
- 仰向けになり、膝を立てて足を腰幅に開く
- 息を吸って準備し、吐きながらお尻をゆっくり持ち上げる
- 上で一度吸い、吐きながら背骨を一つずつ下ろすように戻る
お尻を持ち上げるときは、腰だけを反らせるのではなく、背骨全体を「下から順番に」つなげていくイメージを持つと安全です。
肩をすくめず、体を支える力をお尻とお腹に分散させることがポイントになります。
ペルビックカールで体幹が安定してくると、肩や首に頼らずに動けるようになり、肩こりの根本的なケアにもつながっていくでしょう。
寝る前に数回行うと、全身がほぐれやすくなり、リラックスモードに切り替わりやすくなります。
ピラティスと肩こりに関するQ&A
ピラティスを始めようと思っても、「どのくらいで変化を感じられるのか?」「マシンとマットはどちらがいいのか?」など、気になる点は多いですよね。
ここでは、肩こりケアを目的にピラティスを取り入れる方からよく寄せられる質問をまとめました。
初心者の方でもイメージしやすいよう、効果を感じるまでの目安や、他のエクササイズとの違いについても分かりやすく解説していきます。
どれくらいで肩こり緩和の効果を感じる?
個人差はありますが、週2〜3回のペースで取り組むと、早い人では2週間ほどで「肩が軽い」と感じ始めることがあります。
1カ月ほど続けると、姿勢や呼吸が安定し、こりが戻りにくいと感じる人も増えてきます。
ピラティスは即効性だけを狙うというよりも、「体の使い方を整えていくこと」で肩こりにアプローチするエクササイズです。
続けるほどに肩甲骨や背骨の動きがスムーズになり、結果として血流が良くなりやすいと考えられています。
継続のコツは、完璧を目指さず小さな変化に目を向けることです。朝起きたときの肩の軽さや、呼吸のしやすさに気づくだけでも、モチベーションを保ちやすくなります。
マットピラティスとマシンピラティスはどちらがおすすめ?
肩こりが強い人や体の使い方に不安がある人は、最初はマシンピラティスから始める方が安心な場合が多いです。
マシンはバネのサポートで姿勢を保ちやすく、肩や首に力が入りすぎるのを防ぎながら動きを学べます。
一方で、マットピラティスは自重を使って行うため、自宅でも続けやすく、自分のペースで取り組めるのが魅力です。
体が慣れてきたら、マットを併用することで日常の動作にもピラティスの感覚を生かしやすくなります。
どちらも目的は「正しく体を動かすこと」。通いやすさや予算、ライフスタイルに合わせて選ぶのが、結果的に継続につながりやすいでしょう。
ヨガやストレッチとどっちが肩こりに効く?
ヨガやストレッチも血流を促し、肩こりの軽減にアプローチできる方法です。
ピラティスは、その中でも「筋肉の使い方を変えて再発を防ぐこと」を重視している点に特徴があります。
- ヨガ:柔軟性アップとリラックスにアプローチしやすい
- ストレッチ:一時的なこりの緩和や可動域アップに向きやすい
- ピラティス:姿勢や体幹の使い方を整え、こりにくい体づくりを目指しやすい
ヨガやストレッチは「その場で楽になる感じ」を得やすい一方で姿勢が戻ると、こりも再発しやすいことがあります。
ピラティスは、動きの中で筋肉バランスに働きかけることで、日常の姿勢そのものを変えていくことを目指すエクササイズです。
肩こりが慢性化している場合は、ピラティスで体の土台を整えつつ、その上でヨガやストレッチを組み合わせていくと、より立体的なケアになるでしょう。
ピラティスで肩こりの少ない生活を目指そう

肩こりを感じるたびにマッサージに頼るだけでなく、ピラティスで体の使い方そのものを見直していくことは、長い目で見ると肩こりケアの一つの有力な選択肢になります。
正しい姿勢と呼吸が身についてくると、肩に余計な力を入れなくても日常を過ごせる時間が少しずつ増えていくでしょう。
ピラティスは「頑張りすぎず、続ける」ことが何より大切です。
スタジオに通う日と、自宅での軽いエクササイズを組み合わせながら、生活の中に無理なく溶け込ませていけると理想的です。
体が整ってくると、心も落ち着きやすくなり、呼吸とともに気持ちもふっとゆるむ感覚を味わえるかもしれません。
自分のペースを大切にしながらピラティスを続けて、肩こりに悩まされにくい、軽やかな毎日を目指していきましょう。
※ピラティスの肩こりへの効果や感じ方には個人差があります。
シェアする
ダイエット
ピラティス